私たちが学習・勉強というと、「知識を吸収する」「知識を覚える」「知識を表現する」というように「知識」を中心に考えがちです。
ところがビジネス界には、それとは少し異なる理論があります。「コルブの経験学習理論(モデル)」がそれです。
この理論(モデル)は、アメリカの組織行動学者デイヴィッド・コルブによって提唱された学習理論です。この理論(モデル)によれば、学習とは、「具体的な経験(体験する)」→「内省的な観察(振り返る)」→「抽象的な概念化(気づく)」→「能動的な実践(次の計画を立てる)」→(再び)「具体的な経験・・・」という動きであり、その継続が「成長」だというのです。
つまり、無限に知識を吸収し続けることが「学習・成長」ではなく、自分で自分の体験を振り返り、そこで学んだことを言語化し、次の計画を立てて、再び新しい経験に挑戦していく…この繰り返しこそが人間としての「学習・成長」ということになります。
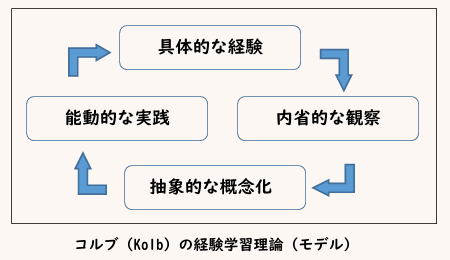
これを具体的な学習の場面で考えてみると次のようになります。
<具体的な経験(体験する)>
実際に算数の問題を解いてみる。例えば、分数の足し算問題に取り組むことで、具体的な課題に直面する。⇒「1/3 + 1/3 + 1/4」を計算する。
<内省的な観察(振り返る)>
問題を解いてみたあと、「どうしてこの答えになったのかな?」と振り返る。間違えた場合には、なぜ間違えたのかを分析することも含まれます。⇒どうして11/12になった?
<抽象的な概念化(気づく)>
問題を解く中で、他の場面にも応用できるルールに気づく。例えば、「分母を最小公倍数で揃える」というルールは、数学的思考の基礎となる。⇒分母を3と4の最小公倍数の12にする。
<能動的な実践(行動計画をつくる)>
学んだルールを次の問題に適用する計画を立てたり、自分で新しい問題を作成して解いてみたりする。⇒「1/2 + 1/3 + 1/6」だったら分母はいくつにそろえるのか?
そして、このサイクルを繰り返すことで、算数(分数計算)の理解力や解く力がどんどん高まっていくというイメージです!
考えることが楽しくなると、次のような問題を考えてみるのもよいかもしれません。
問題:ピザを3人で分けました。2人はそれぞれ1/3ずつ食べ、もう1人は1/4食べました。残りのピザはどれだけですか?
このような身近な場面を使って考える力を育むことが、算数をさらに楽しくする鍵です!
さて、答えは分かりましたか?(ヒントはこの文章中にありますよ。それぞれの食べた量を足して、残りを計算してみてください。)
◎主に参考とした本:デイヴィッド・コルブ、 ケイ・ピーターソン、 中野眞由美『最強の経験学習』辰巳出版 2018年
◎主に参考とした本:松尾睦『職場が生きる 人が育つ 「経験学習」入門』ダイヤモンド社 2011年
前のページ(学習方法 1-7 学習に対する考え方(学習観))はこちらからどうぞ
